「どうして、うちの子はじっとできないんだろう?」
「何度言っても立ち上がってしまう…私の育て方が悪いの?」
そんなふうに、周囲の視線や声に傷つきながら、今日も必死で我が子と向き合っているお母さん、お父さんへ。
このページにたどり着いたあなたは、それだけで、もう“十分にがんばっている人”です。多動傾向のあるお子さんとの日々は、「普通」に当てはめようとすればするほど、親の心がすり減ってしまいます。
でも、ひとつお伝えしたいのは――
「あなたのお子さんは、ただちょっと“違うペース”を持っているだけ」だということ。
このシリーズでは、発達障害の特性を理解しながら、
✅ 日々の子育てが少し楽になるヒント
✅ 親としての心の保ち方
✅ 自然な方法で子どもをサポートする方法の可能性
について、わかりやすくお届けしていきます。
どうか一人で抱え込まずに、まずは読みながら「ふぅ」と深呼吸してください。
この記事の目次
多動性とは?ADHDとの関係

「多動性」とは、落ち着きがなく、常に動いていたいという衝動的な行動傾向を指します。これは、発達障害のひとつであるADHD(注意欠如・多動性障害)の主要な特性のひとつです。
ADHDの子どもは、以下のような行動を日常的に示すことがあります。
・じっと座っているのが難しい
・授業中や食事中に立ち歩いてしまう
・手足をバタバタ動かしたり、体をくねらせたりする
・順番を待つことに強いストレスを感じる
・静かに遊ぶことが苦手
こうした行動は、決して「わざと」「親のしつけが足りない」ことが原因ではありません。子ども自身が「落ち着きたい」「言われた通りにしたい」と思っていても、うまく自分の身体や気持ちをコントロールできない――それが多動性の本質です。
脳の仕組みとの関係
近年の脳科学では、ADHDの子どもには脳の前頭前野という領域の働きに違いがあることが明らかになっています。前頭前野は「注意を集中する」「感情を調整する」「衝動を抑える」など、まさに“自分をコントロールする”機能を担っています。
また、ADHDでは以下のような神経伝達物質の不均衡も見られます。
・ドーパミン:やる気・注意力に関係し、不足すると集中が続きません
・ノルアドレナリン:注意力や覚醒に関係し、感情の調整に関わります
これらの物質が脳内でうまく機能しないことが、注意散漫や多動といった行動につながるのです。
成長と共に変化することも
なお、多動性の特性は年齢とともに変化していくことがあります。幼少期には身体の多動が目立っていた子も、思春期や成人になると外から見える多動は減り、「頭の中が落ち着かない」「じっとしていても心がそわそわする」といった“内的な多動”へと移行することがあります。
親の悩みーー「うちの子だけが変なの?」という孤独

多動性のある子どもを育てている親御さんは、日常的に周囲の目や評価、そして自身の葛藤に苦しんでいます。これは単なる“育てづらさ”ではなく、子どもの特性に起因する予測しづらい行動に対し、親として社会的・心理的な重圧を抱える状態です。
よくある親の悩みと心理的影響
以下は、多動傾向のある子どもを持つ保護者が訴える主な悩みです:
・周囲から『しつけが悪い』『甘やかしている』と思われる
・保育園・幼稚園・学校から頻繁に呼び出される
・公共の場で騒いだり走り回ったりして、人目が気になる
・きょうだいとの関係に気を配るあまり、家庭内の緊張が続く
・自分自身の気持ちに余裕がなくなり、落ち込んだり孤立感を抱える
専門家が見る”親の孤独と二次的ストレス”
発達障害児を育てる保護者は、慢性的な“ケアラー・ストレス(caregiver stress)”にさらされていると指摘されています。子どもの行動を常に見守り、予測不能なトラブルに対応し続けることは、心身の疲労につながります。
また、親が社会から受ける無理解や偏見(例:『親のしつけの問題』という決めつけ)は、“スティグマ(社会的烙印)”となり、親自身の自己肯定感を著しく低下させます。これが長期間続くと、うつ状態や身体症状(頭痛・不眠など)を伴うこともあります。
家庭内でのバランスの難しさ
多動性のある子どもへの対応に追われる中で、他のきょうだいとの関係やパートナーとのすれ違いも生じやすくなります。これを“家族全体の心理的巻き込み”と呼び、家族関係の調整や親のメンタルヘルス支援が必要になるケースもあります。
親が“完璧な対応”を目指すあまり、自分を追い込んでしまうことも少なくありません。時には、少し肩の力を抜いて「困った時は助けを求める」ことも大切です。
解決の糸口は”つながり”と”情報”
同じ悩みを抱える保護者との交流(ピアサポート)や、支援団体・カウンセラーとのつながりが、孤独を和らげる大きな助けになります。
また、ADHDや多動性に関する正しい知識を学ぶことで、子どもに対する理解が深まり、親自身も自分を責めすぎずにすむようになります。
“うちの子だけが変なんじゃないか…”と悩むのは、あなただけではありません。見えないストレスを言葉にし、つながることで、親としての心の余裕を取り戻していけるのです。
対処法①:環境の調整で「失敗しにくい場」をつくる
多動性のある子どもにとって、動くことを制限される環境は“我慢の連続”となり、ストレスや問題行動の原因になります。そのため、無理に子どもを変えようとするのではなく、子どもが“自然に過ごせる環境”を整えることが、最も効果的な支援の第一歩です。
環境調整とは『行動を成功に導くための工夫』
環境調整とは、子どもが持つ特性に配慮しながら、行動しやすく・落ち着きやすくなるように“周囲の環境そのもの”を工夫する支援方法です。これは「応用行動分析」にもとづく実践的アプローチのひとつで、子どもの成功体験を増やすことが目的です。
実践例:家庭や教室でできる調整
●動いてもOKな椅子の工夫
バランスボールやバランスクッションを使うと、座りながら揺れたり体幹を使ったりすることで、過剰な動きを“座ったまま放出”できます。これにより、他の子と同じように授業や作業に参加しやすくなります。
●安全に動けるスペースの確保
狭い通路や家具の多い部屋では、動こうとするたびに注意されたり、ケガのリスクが高まります。室内に1~2畳分程度の“自由に動けるゾーン”を確保することで、衝動的な動きにも柔軟に対応できます。
●タイマーやスケジュール活用
集中できる時間を10分など短く区切り、タイマーを使って『集中→休憩→再開』のリズムを作ります。これにより、長時間じっとするプレッシャーから解放され、自分のペースをつかむ練習になります。視覚的に時間を示せる“タイムタイマー”などを活用すると、特に効果的です。
『動いてもいい』というメッセージが自己肯定感を育てる
多動傾向のある子どもは、“いつも叱られる存在”になりがちです。しかし、動きが許容される環境では、子どもは『自分はここにいていいんだ』『頑張ればできる』という自己肯定感を育むことができます。
環境を整えることは、子どもの問題を減らすだけでなく、その子らしさを受け入れることにもつながります。
対処法②:褒め方の工夫で自己肯定感を育てる
多動性のある子どもは、日常生活で「ダメ」「またやったの?」と注意される経験が多く、成功体験が少なくなりがちです。その結果、自信をなくし「どうせまた怒られる」と思い込み、行動への意欲を失ってしまうこともあります。
褒めることの心理学的効果
心理学では、行動が強化されるためには“成功体験の積み重ね”が重要とされています。これは『正の強化(positive reinforcement)』と呼ばれ、望ましい行動が再び起きる確率を高めます。
褒めるポイント:量より質
「今日は3分間座っていられたね」「最後まで手を動かしてたね」など、結果ではなく“努力の過程”を評価することが鍵です。子どもが『自分の頑張りを見てくれている』と実感できる声かけは、自己肯定感を育みます。
また、具体的に褒めること(例:「静かにできていたね」)は、子どもが“どの行動がよかったのか”を理解しやすくなり、次回の行動にもつながります。
対処法③:感覚統合・ボディワークで身体感覚を育てる
多動性のある子どもは、自分の体の位置や力加減がつかみにくい“感覚統合の未発達”が見られることがあります。これは神経発達の特性によるものであり、感覚統合を促す運動を通じて改善が期待できます。
感覚統合とは
視覚、聴覚、前庭覚(バランス感覚)、固有受容覚(体の位置や筋肉の感覚)など、さまざまな感覚情報を統合し、適切に行動するための脳の働きです。感覚統合が未発達だと、過剰に動いたり、逆に動きがぎこちなくなることがあります。
おすすめの感覚刺激アクティビティ
・トランポリン、バランスボード(前庭感覚)
・回転遊び、スキップ、ジャンプ運動
・ブランコやハンモックでゆらゆら揺れる
・ディーププレッシャー:肩や手足をやさしく圧迫することで安心感が得られる
これらの活動は、セラピストが行う“感覚統合療法”の一部を、家庭でも簡易に取り入れる方法として有効です。
対処法④:「頑張りすぎる親」から卒業する
発達特性のある子どもを育てる親は、常に気を張りつめていたり、自分を責めすぎてしまう傾向があります。しかし“がんばりすぎ”は、親自身の心と体を消耗させ、結果として子どもにも不安が伝わってしまいます。
親のバーンアウト(燃え尽き症候群)とは
慢性的なストレスにより、親が精神的・身体的に疲弊する状態。ADHDの子育てでは特に起こりやすいとされており、早期に気づいて対処することが大切です。
自分の時間を持つことの大切さ
“子どもから離れる時間”を作ることは悪いことではありません。親自身がリラックスする時間を確保することで、心に余裕が生まれ、子どもにも優しく関わることができるようになります。
また、地域の支援機関やカウンセラーとの連携、他の保護者との交流など“誰かとつながる”ことが、親の孤独感や不安を和らげる大きな支えになります。
自然な調整力を引き出す「フランス式耳介療法」という選択肢
フランス式耳介療法(オリキュロセラピー)は、耳の反射点を刺激することで神経系や内臓、自律神経にアプローチする療法です。1950年代にフランスのポール・ノジェ博士が体系化し、WHOでも認められている代替医療のひとつです。
フランス式耳介療法講習 〜発達障害を支えるお母さんへ〜
子どもの発達の相談は、専門医のもとだけでは限りがあります。通院は時間もお金もかかり、1〜2回で完治するものでもありません。そんな中、日常に取り入れられるケアとして「フランス式耳介療法」があります。
• お母さん自身が“家庭での主治医”に
専門医に頼り切るのではなく、耳にあるツボのセルフケアを学ぶことで、日々の変化に気づける存在に。
• 通院負担を減らし、持続できる支援に
毎回外出するのが難しい方も、ゆっくり少しずつ続けられるプログラムだから安心。
• “よくなっていく過程”を楽しむ
一度の施術で終わるものではありません。お子さんの少しずつ変化する様子を、見守りながら喜びに変えていく時間になります
こんな方にぴったり!
• 専門医に頼りすぎず、自分でサポートできる力を身につけたいお母さん
• 子どもの小さな変化を日々キャッチできるケアをしたい方
• 長い目で、家族みんなで取り組める療法を探している方
耳と脳の神経学的つながり
耳には、迷走神経・三叉神経・顔面神経など、脳と直結する重要な神経が集中しています。このため、耳へのやさしい刺激が脳全体に働きかけ、特に自律神経の調整に効果があるとされています。
多動性に対する耳つぼの位置

・神門:情緒の安定、リラックス
・前頭葉:集中力と抑制力に関与
・扁桃体:行動や精神状態のコントロール働きかける
これらの部位に、専用の耳つぼシールを使って刺激することで、薬に頼らず自然な調整力を引き出す補完的アプローチとして活用されています。
おわりにーー「違い」は可能性でもある
多動性のある子どもたちは、環境や理解が整えば、自分らしくのびのびと成長していける力を持っています。子どもの行動には必ず“意味”があり、そこに寄り添う視点が、親にも子にも新しい道を開く鍵になります。
叱るのではなく環境を整える、押さえつけるのではなく認めて伸ばす、そして“がんばりすぎない親”になること。その積み重ねが、子どもたちが自分らしく生きていく土台となるのです。
《監修者》この記事を書いた人

田中 幸恵
一般社団法人ジャパンセラピスト検定機構代表理事
耳介療法士・心理カウンセラー・夫婦カウンセラー
国際耳介療法学会会員
耳つぼの講師
カウンセリング歴30年。
2014年に耳介療法の元祖Dr.ポール・ノジェの子息であるDr.ラファイエル・ノジェ(現在国際耳介療法学会 CEO)より直々に耳介療法を学ぶ。耳の不思議さと奥深さに魅せられ、もっと多くの方に広めたいという想いから、今まで学んでいた中国式耳つぼ療法とフランス式耳つぼ療法を融合した独自メゾット「新フランス式オリキュロセラピー」を完成。
ご家族や大切な人の健康に貢献したい方、セラピストとしてさらに結果を出したい方に「耳つぼ療法」を通してミラクルを起こすお手伝いをしている。


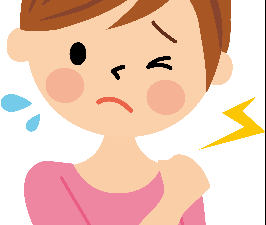
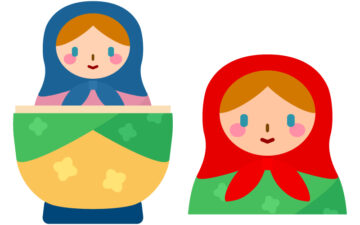




この記事へのコメントはありません。