「この順番じゃないとダメ!」「決まった服しか着たくない」「毎日同じルートで通わないとパニックになる」そんな“こだわりの強さ”を持つお子さんに悩んでいる親御さんは多いのではないでしょうか。
今回は、発達障害の特性のひとつである「こだわり行動」について、親の悩み、対応策、そして自然療法の有効性を含めてご紹介します。
この記事の目次
こだわりとは? ASDに多く見られる特徴

発達障害、とくにASD(自閉スペクトラム症)の子どもによく見られる特性のひとつが、「こだわり行動」です。これは単なる「気まぐれ」や「頑固さ」ではなく、脳の認知や情報処理の特性によって生じる、安心感を得るための行動パターンなのです。
こだわり行動とはどういうもの?
ASDの子どもは、予測できない変化や曖昧な状況に対して強い不安を感じやすい傾向があります。そのため、「いつも通り」「自分の中のルール通り」であることが、安心の土台になります。
のような背景から、特定の順番やパターン、感触、環境へのこだわりが現れるのです。
よくある”こだわり”の例
・同じ服ばかり着たがる
肌ざわりや着心地が“安心できる感覚”と結びついており、他の服では不快に感じる(触覚過敏の影響も)
・食事の並べ方や順番に強いこだわり
「毎日同じ順序で進むこと」が安心であり、少しの変化でも混乱や不安を感じやすい
・決まった道で登下校したがる
知っている景色やルートでないと、予測ができず強い不安が生じる(見通しの欠如に対する防衛)
・数字や時計の時間に過剰に反応する
数字は「正確で裏切らないもの」として安心材料になりやすく、そこに強く依存するケースも
脳の特性とこだわりの関係
ASDの子どもたちは、脳の機能的な特徴として以下のような傾向をもっています:
• 柔軟性の低さ(認知的柔軟性の障害)
→ 予定変更や予想外の出来事への適応が苦手
• 感覚過敏・鈍麻の共存
→ 感覚のズレを抱えているため、「同じ」であることが唯一の安心材料になる
• 中央統合(情報を統合する力)の弱さ
→ 状況を総合的にとらえることが難しく、部分的なルールに強く固執する傾向がある
これらの脳の働きが、「こだわり行動」として表れているのです。
周囲からの誤解との向き合い方
こだわりの強さは、ときに周囲から「わがまま」「育て方の問題」と誤解されることがあります。しかし、本人にとってはそれが安心を保つための“自己防衛”の方法であり、無理に変えようとすることはかえって逆効果になることもあります。
「変えさせる」のではなく、「理解し、寄り添う」ことが第一歩です。
親の悩みー「また始まった…」というストレスと罪悪感

こだわりが強い子どもと向き合う日々は、予測がつかず、気が休まらない連続になりがちです。とくに予定外のことが起こったとき、家庭の中でも外でもトラブルに発展しやすく、親としてのストレスが積み重なっていきます。
• 朝の予定が少し変わっただけで、大泣きやパニックに発展してしまう
• 兄弟姉妹との遊びや生活でも、「自分ルール」にこだわって衝突が起こる
• 外出中に予想と違うことがあると、その場で動けなくなったり怒り出したりする
そうした場面に直面するたび、親は思わず「また始まった……どうしてうまく対応できないんだろう」と、疲れや自己否定の感情に襲われてしまいます。そして、子どもが落ち着いたあと、「あの時もっと上手に言えば」「回避できたかも」と、自分を責めてしまう親御さんも多いものです。
特に周囲の目や学校・保育園からの指摘があると「私の育て方が悪いのでは」と、自分自身を疑ってしまうことも少なくありません。
こだわり行動の背景には、たいてい不安や感覚過敏、脳の認知の特性があります。つまり、それは「わざとやっている」のではなく、“感じ方の違い”が行動に表れているだけなのです。例えるなら、「予定変更が頭の中でうまく整理できない」といった苦しさを避けるための自己防衛反応とも言えます。
無理に直そうとするのではなく、「理解する姿勢」から
強いこだわりは、しばしば「成長に悪影響では?」と心配されがちですが、実はそれを頭ごなしに否定することのほうが、子どもの自己肯定感を下げるリスクになります。
無理やり変えようとすると、不安感が強まり、反発や閉じこもりが激化することもあります。逆に、「この子はこう感じているんだ」と理解しようとする姿勢は、信頼と安心感につながる第一歩になります。
子どものこだわりに毎回うまく対応するのは、とても難しいことです。うまくできなかった日があっても、それは親としてダメだったわけではなく、人間として当然のこと。
むしろ大切なのは、「この子にとって、何が不安だったんだろう?」と、毎回少しずつ振り返りながら関わっていく姿勢です。
発達障害における”こだわり行動”の対処法① 安心の「予告」と「選択肢」を与える
こだわりが強く出やすい子どもにとって、「これから何が起きるか分からない」ことは、大きなストレスになります。そのため、あらかじめ“見通し”を伝えておくことで、不安やパニックをぐっと減らすことができます。また、小さな選択肢を用意して“自分で決められた”という感覚を持たせると、心に余裕が生まれやすくなります。
実践例
• 「あと10分で出かけるよ」と時間を予告
→ いきなり動こうとせず「タイマーをセットして、音が鳴ったら準備を始めようね」と視覚的・聴覚的に伝えるのも効果的です。
• 「今日は2つの道、どちらで行こうか?」と選択肢を与える
→ 「絶対にこの道じゃないとダメ!」という子も、自分で選んだという満足感があると、比較的スムーズに行動に移れます。
• 絵カードやスケジュール表で予定を可視化する
→ 文字では理解が難しい子でも、イラストや写真で一日の流れが見えると安心につながります。予定が変わるときは、「☓マーク」「→に変更」など視覚的に示す工夫も有効的です。
その他の活用シーン
• 朝の身支度:「先に顔を洗う?それともお洋服着る?」と選ばせることで、指示に対する反発が減る
• 遊びの終わり:「あと5分でお片づけね。あと1回だけブロック積みしようか?」と“区切り”を予告
• 病院や美容院など:「先に何をするか、終わったら何があるか」を伝えることでパニックを回避
• 外食時:「この2つのメニューならどっちがいい?」と限られた範囲で選ばせることで混乱を防ぐ
「こだわり」を“押さえつける”のではなく、事前に「安心」を渡してあげることで、子どもは自分のペースで状況に向き合えるようになります。少しの工夫で、親子ともに過ごしやすい時間が増えていきますよ。
発達障害における”こだわり行動”の対処法②「安心アイテム」を許可する
こだわりのある子どもは、日常の中で不安を感じやすく、その不安を和らげるために“特定のもの”に強く執着することがあります。
• いつも同じぬいぐるみを持ち歩く
• 決まったタオルや毛布でしか寝られない
• 同じ服しか着たがらない など
これらは単なる「わがまま」ではなく、子どもにとっては「心を落ち着ける支え」=安心アイテムなのです。
工夫の具体例
• 保育園や学校に持って行けるよう小型化する
例:「お気に入りのタオルの一部を切ってハンカチサイズにする」「ぬいぐるみのキーホルダーを作る」
持ち込めない場合も、「ポケットに入れられるサイズ」にすることで対応できることがあります。
• 似た素材や感触のものを用意する
例:「洗い替え用の同じ素材の服を探す」「似た手ざわりのハンカチを選ぶ」
触覚過敏がある子には“感触の違い”が大きなストレスなので、類似素材を準備しておくと安心です。
• 家の中だけのルールをつくって許可する
例:「リビングではOKだけど外出時は持ち歩かない」「寝るときだけ使える“安心毛布”」
完全に禁止するのではなく、安心できる場面でのみ許すルールがあると、本人も納得しやすくなります。
発達障害における”こだわり行動”の対処法③「崩れても大丈夫」を体験で学ぶ
こだわりの強い子どもにとって、予定が変わることや順番が乱れることは“大事件”です。ですが、そうしたこだわりを少しずつゆるめていくには、成功体験を通じて「崩れても平気だった!」と感じることが何より大切です。
少しずつ慣れるための工夫例
• 遊びの中で順番を変える体験
例:「いつも積み木から始めているところを、今日はパズルから」「すべり台→ブランコを逆にしてみる」
楽しさの中で自然に順番が変わっても問題ない経験を積むことで、柔軟性が育ちます。
• 「今日は違うお皿でも楽しいね」などのポジティブな声かけ
決まった食器が使えないときでも、「いつもと違うけど面白いね」「この色も似合ってるね」など肯定的な表現で気持ちをほぐします。
• 成功したときにはしっかり褒める
小さな変化を乗り越えられたときには、「今日は違う道だったけどがんばったね」「新しい服でも大丈夫だったね」とその子にとっての挑戦をきちんと認めてあげることが大切です。
変化に対する不安をなくすことはできなくても、「やってみたら案外平気だった」「失敗しても怒られなかった」という体験の積み重ねは、少しずつ心に“余白”を生んでくれます。
こだわりや不安にアプローチする自然療法
「これじゃなきゃダメ」「順番が変わると不安で泣き出す」
――そんな強い“こだわり”の背景には、脳の緊張や感覚の過敏さが深く関係していることがあります。
子どもの心と体を、やさしく整えてあげたい。そんな想いに寄り添うケアとして、注目されているのがフランス式耳介療法(オリキュロセラピー)です。
フランス生まれの自然療法 ― 耳から“安心”を届ける
耳介療法は、耳にある反射区(ツボ)をやさしく刺激することで、脳や神経系に働きかけるシンプルでやさしい自然療法です。フランスでは医療現場や教育現場でも活用されており、子どもや敏感な人への補助的ケアとして広く知られています。
子どもの“こだわり”と向き合う3つの働き
耳介療法では、次のようなポイントを中心にやさしく刺激していきます。

• 「神門」や「情緒安定」のツボ:リラックスを促し、不安を和らげる
• 「前頭葉」や「ストレス調整」ゾーン:考えすぎや固くなった思考をほぐし、柔軟な心の動きをサポート
• 痛みのないソフトな刺激:貼る・触れるだけでOK。怖がりな子どもでも受け入れやすく、家庭でも簡単に実践できます
学んだその日から、わが子のケアに
「施術って難しそう…」と思われるかもしれませんが、ご安心ください。
フランス式耳介療法では専用の探索機(探知器)を使って、耳の中にある“緊張や不調のサイン”を見つけ出します。なので、特別な経験や知識がなくても、誰でも正しい場所にアプローチできるようになります。
1日の講座で「理論と実践」を丁寧に学ぶことができ、学んだその日からご家庭でのケアが始められます。
自然に、無理なく、親子で心を整える時間を
お薬や叱ることでは届かない子どもの不安に、やさしく触れるケアで寄り添う――
フランス式耳介療法は、そんな“親の手から伝わる安心”を大切にした自然療法です。
こだわりや不安で生きづらさを感じているお子さんの心に、少しでもやわらかな光が差し込むように。
一緒に、耳から始めるやさしいケアを学んでみませんか?
まとめ
子どもの「こだわり」は、時に周囲を戸惑わせたり、対応に悩んだりすることもあります。でもそれは、自分の世界を守るための“安心の枠組み”であり、本人なりの理由がちゃんとあるのです。
無理に変えようとせず、「この子にはこう見えているんだ」と受け止めてあげること。
そして少しずつ、「崩れても大丈夫だった」「新しいことにもチャレンジできた」といった小さな成功体験を積み重ねていくことが、その子の世界を広げていく大きな一歩になります。
親ができることは、完璧な対応ではなく、安心できる場所と関わりを整えてあげること。そして、子どもが「自分らしく」生きられるように、日々そっと寄り添い続けることです。
そんな優しいケアのひとつとして、フランス式耳介療法のような自然な調整法も、子どもの心と体にそっと寄り添う力になってくれるかもしれません。
今日のこだわりも、明日の安心につながる。そう信じて、一歩ずつ、ゆっくり歩んでいきましょう。
《監修者》この記事を書いた人

田中 幸恵
一般社団法人ジャパンセラピスト検定機構代表理事
耳介療法士・心理カウンセラー・夫婦カウンセラー
国際耳介療法学会会員
耳つぼの講師
カウンセリング歴30年。
2014年に耳介療法の元祖Dr.ポール・ノジェの子息であるDr.ラファイエル・ノジェ(現在国際耳介療法学会 CEO)より直々に耳介療法を学ぶ。耳の不思議さと奥深さに魅せられ、もっと多くの方に広めたいという想いから、今まで学んでいた中国式耳つぼ療法とフランス式耳つぼ療法を融合した独自メゾット「新フランス式オリキュロセラピー」を完成。
ご家族や大切な人の健康に貢献したい方、セラピストとしてさらに結果を出したい方に「耳つぼ療法」を通してミラクルを起こすお手伝いをしている。




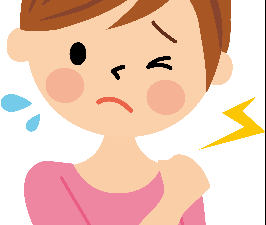



この記事へのコメントはありません。